86歳女性。誤嚥性肺炎で入院し、栄養障害もあったため経鼻経管栄養を実施し退院した。本人の希望により娘の介助のもとで在宅にて療養をしている。薬局薬剤師が在宅訪問を行うにあたり、介護支援専門員から、「本人より、経管栄養をやめてほしいという要望がある。」と報告された。一方、在宅訪問の際、家族からは「なんとか元気になってほしいので、経管栄養を続けてほしい。」との意向を聴取した。
問320(実務)
薬剤師の対応として、適切なのはどれか。2つ選べ。
- 患者より家族の意見を優先すべきなので、介護支援専門員からの報告は考慮しなかった。
- 経管栄養をやめてほしいという意思について、再度患者に確認し、何故そのように思ったのか聞き取りをした。
- 患者の意思に従って、薬剤師が経管栄養の管を抜去した。
- 医師や在宅医療に関わる多職種と情報共有し、患者や家族と話し合った。
- 担当医師の方針に同意しなければ、在宅医療を継続できないことを患者に伝えた。
解答・解説
解答
2、4
解説
1 誤
患者、家族の意見、双方を考慮し、治療方針を決定する必要があるため、介護支援専門員からの報告も考慮する必要がある。
2 正
患者の意見を把握した上で、治療方針を決定する必要があるため、患者の意向を再度確認する必要がある。
3 誤
経管栄養の管を抜去することは医師等が行うことであり、薬剤師は行うことができない。
4 正
医療従事者(医師、在宅に関わる多職種)間で情報を共有し、患者、家族と話し合い、治療方針を決定する必要がある。
5 誤
担当医師の方針に同意しなくても、在宅医療を継続することが可能である。
問321(法規・制度・倫理)
この患者の要望の様な患者の意思及び自己決定を尊重する考え方について述べている、世界医師会総会が採択した宣言はどれか。1つ選べ。
- ヘルシンキ宣言
- ジュネーブ宣言
- バルセロナ宣言
- リスボン宣言
- 世界人権宣言
解答・解説
解答
4
解説
1 誤
ヘルシンキ宣言(ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則)は、1964年にフィンランドの首都ヘルシンキで開かれた世界医師会において採択された人体実験に対する倫理規範であったが、現在では人間を対象とする医学研究の倫理的原則として適用されている。 なお、医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP)は、ヘルシンキ宣言の理念に準拠した基準である。
2 誤
ジュネーブ宣言は、1948年の世界医師会総会で採択されたものであり、医の倫理に関する規定である。
3 誤
バルセロナ宣言は、ヨーロッパにおける生命倫理の基本的な倫理原則である。
4 正
リスボン宣言は、世界医師会で採択された患者の権利宣言である。リスボン宣言には、患者の自己決定権が示されている。
5 誤
世界人権宣言は、1948年にパリで行われた国連総会において採択されたものであり、基本的人権尊重の原則を定めたものである。
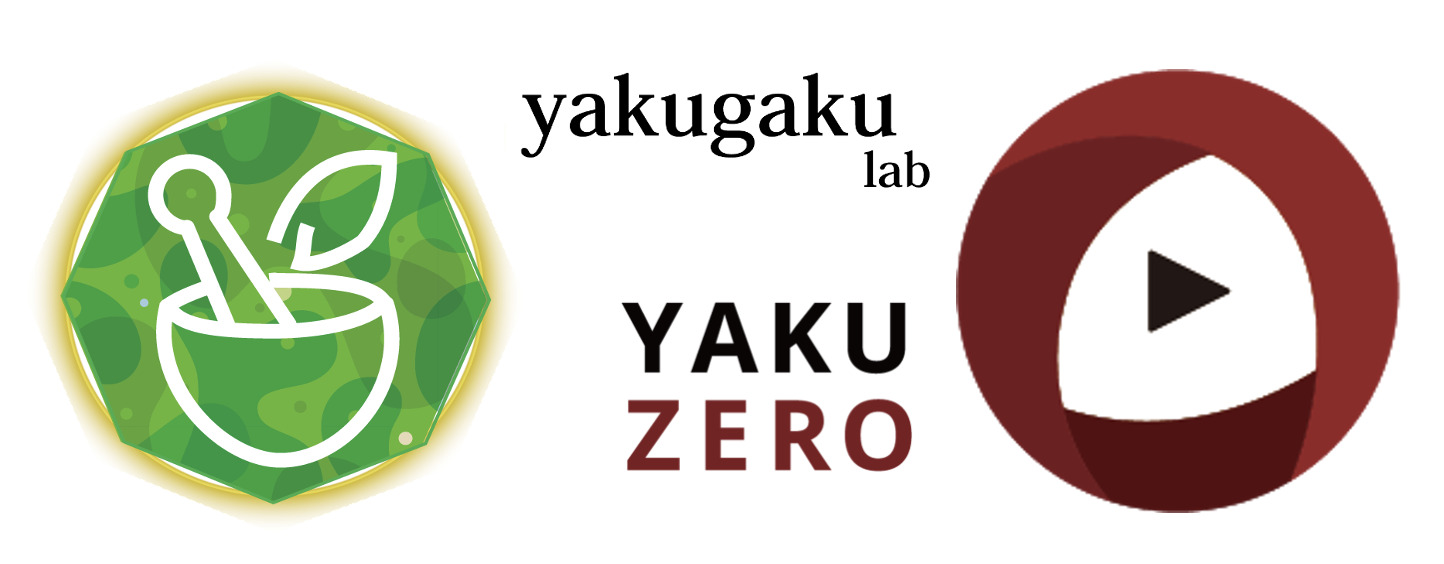

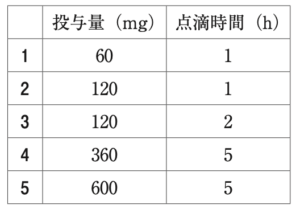




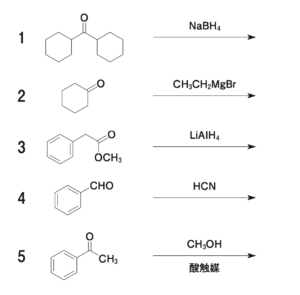

コメント