65歳女性。5年前より高血圧症を指摘されていたが、自覚症状がなく放置していた。数日前より頻回に動悸と気分不良を自覚するようになり、循環器内科を受診した。血圧124/86mmHg、心拍96拍/分(不整)であった。心電図などの諸検査の結果、心房細動と診断され、抗凝固薬が投与されることになった。
問159(病態・薬物治療)
この患者の病態と治療に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 心電図所見では、P波が消失し、不規則なRR間隔が認められる。
- 心房細動の重症度判定に、NYHA分類が用いられる。
- 心拍数の調節には、リドカイン点滴静注を用いる。
- 1回拍出量は、心房細動の発症前と比べて低下している。
- 無治療で洞調律に戻ることはない。
解答・解説
解答
1、4
動画解説
解説
1 正
心房細動における心電図所見ではP波が消失し、基線が乱れた状態となり、不規則なRR間隔が認められる。
2 誤
心房細動の重症度判定には、NYHA分類は用いられない。なお、NYHA分類は自覚症状による心不全重症度の分類である。
3 誤
リドカイン点滴静注は、期外収縮、発作性頻拍の治療に用いられるが、心拍数の調節には用いられない。なお、心拍数の調節には、β受容体遮断薬、非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、ジギタリス製剤、アミオダロン塩酸塩が用いられる。
4 正
心房細動では、心房の収縮が不完全になり、血液が心室に十分に送られなくなることで、1回の心拍出量が低下する。
5 誤
心房細動には、発作性心房細動、持続性心房細動、長期持続性心房細動がある。発作性心房細動では、無治療で洞調律(正常な脈)に戻ることがあるが、持続的に心房細動が継続すると、無治療で洞調律に戻りにくくなる。
問160(薬理)
抗凝固薬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ナファモスタットは、アンチトロンビンと複合体を形成して、第Xa因子を阻害する。
- ダナパロイドは、アンチトロンビン非依存的に第Xa因子を直接阻害する。
- リバーロキサバンは、トロンビンに結合してプロテインCを活性化することで、トロンビンを直接阻害する。
- ワルファリンは、ビタミンKエポキシド還元酵素を阻害することで、ビタミンK依存性凝固因子の生成を阻害する。
- ダビガトランエテキシラートは、体内で活性代謝物となり、トロンビンを直接阻害する。
解答・解説
解答
4、5
解説
1 誤
ナファモスタットは、タンパク質分解酵素阻害薬であり、アンチトロンビンⅢ非依存的にトロンビン及び第Ⅹa因子などのタンパク分解酵素活性をもつ凝固因子を阻害する。
2 誤
ダナパロイドは、アンチトロンビン依存的に第Ⅹa因子を阻害する。
3 誤
リバーロキサバンは、アンチトロンビン非依存的に第Xa因子を直接阻害する。
4 正
ワルファリンは、ビタミンKエポキシド還元酵素を阻害することで、ビタミンK依存性凝固因子(プロトロンビン、第Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因子)の生成を阻害する。
5 正
ダビガトランエテキシラートは、体内で活性代謝物となり、トロンビンを直接阻害する。
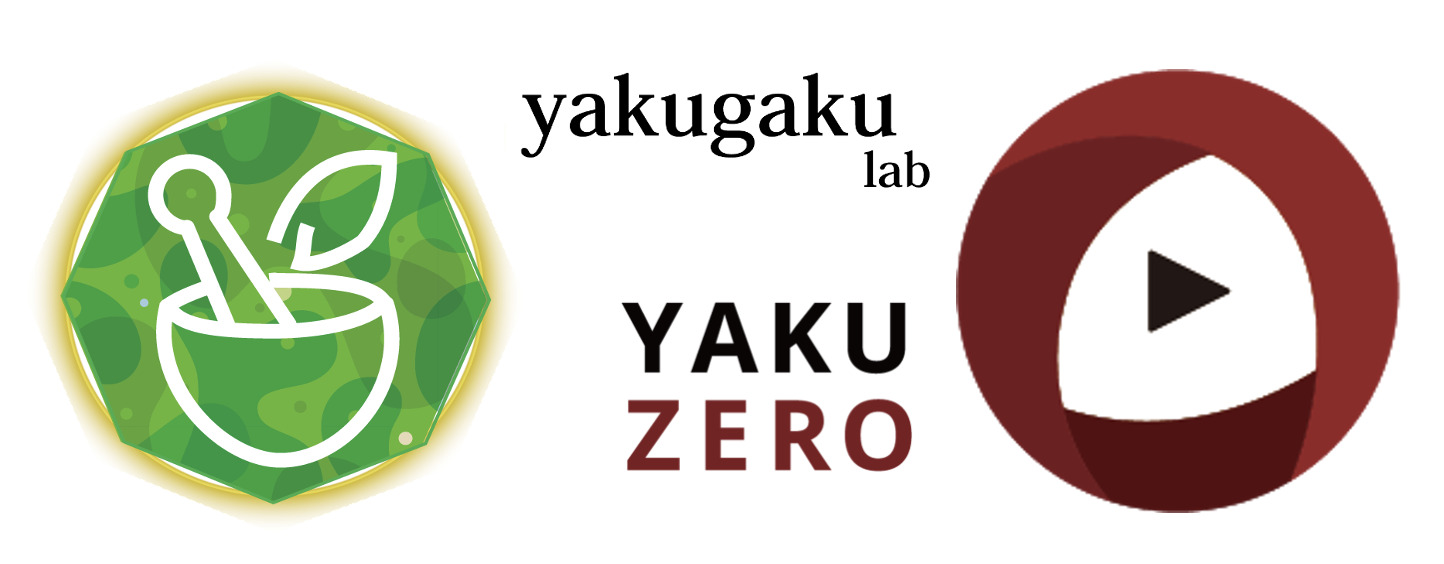

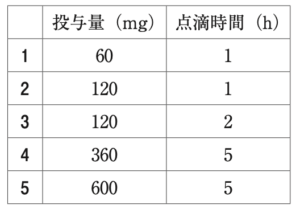




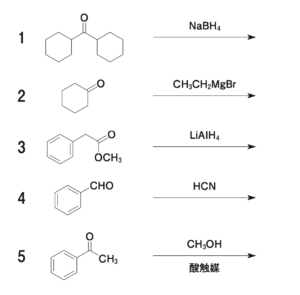

コメント