40歳男性。8月3日の早朝、下痢、腹痛、嘔吐と発熱を訴えて救急外来を受診した。医師が問診したところ、前夜に友人5人とイカ釣りに出かけ、船上で釣ったイカをイカそうめん(細切りの刺身)にして食べたとのことであった。友人5人も同様の症状を訴えているという。医師は食中毒と診断し、便の検査をオーダーするとともに、薬剤師に治療薬についての処方提案を求めた。
問228 (衛生)
この症例において、食中毒の原因として最も可能性が高いのはどれか。1つ選べ。
- サルモネラ属菌
- ノロウイルス
- アニサキス
- 腸炎ビブリオ
- ウェルシュ菌
解答・解説
解答
4
解説
本問の時期は8月3日(夏期)であり、魚介類(イカ)の生食により下痢、腹痛、嘔吐、発熱などの食中毒症状を示していることから、この食中毒の原因として最も可能性が高いのは「腸炎ビブリオ」である。
1 誤
サルモネラ属菌による食中毒は、動物の糞尿により汚染された鶏卵、食肉などが原因となることがある。
2 誤
ノロウイルスによる食中毒は、カキなどの二枚貝の生食などが原因となることがある。
3 誤
アニサキスによる食中毒は、魚介類の生食などが原因となることがあり、冬期に発生しやすい。細切りされたイカでは、アニサキスによる食中毒が起こることが稀である。
4 正
5 誤
ウェルシュ菌による食中毒は、肉類や魚介類を加熱調理後放置されたものを食することが原因となることがある。
問229 (実務)
この患者の初期の治療に最も適した薬剤はどれか。1つ選べ。
- セフェム系抗菌薬
- 電解質輸液
- 止瀉薬
- 解熱鎮痛薬
- 鎮痙薬
解答・解説
解答
2
解説
腸炎ビブリオによる食中毒では、下痢や嘔吐により水分や電解質が失われることがある。そのため、腸炎ビブリオによって起こった食中毒に対しては、水分や電解質を補うために電解質輸液の点滴を行う。
1 誤
腸炎ビブリオによる食中毒では、電解質輸液を投与することで数日中に回復することが多いため、抗菌薬の投与は必要ない。なお、症状が重篤な場合には、ニューキノロン系抗菌薬などを投与することがある。
2 正
3 誤
止瀉薬や鎮痙薬を用いると、腸管に存在する腸炎ビブリオの排泄を抑制することがあるため、止瀉薬や鎮痙薬を腸炎ビブリオによる食中毒の治療に用いることはない。
4 誤
解熱鎮痛薬を用いると、脱水症状を悪化させることがあるため、解熱鎮痛薬を腸炎ビブリオによる食中毒の治療に用いることはない。
5 誤
解説3参照
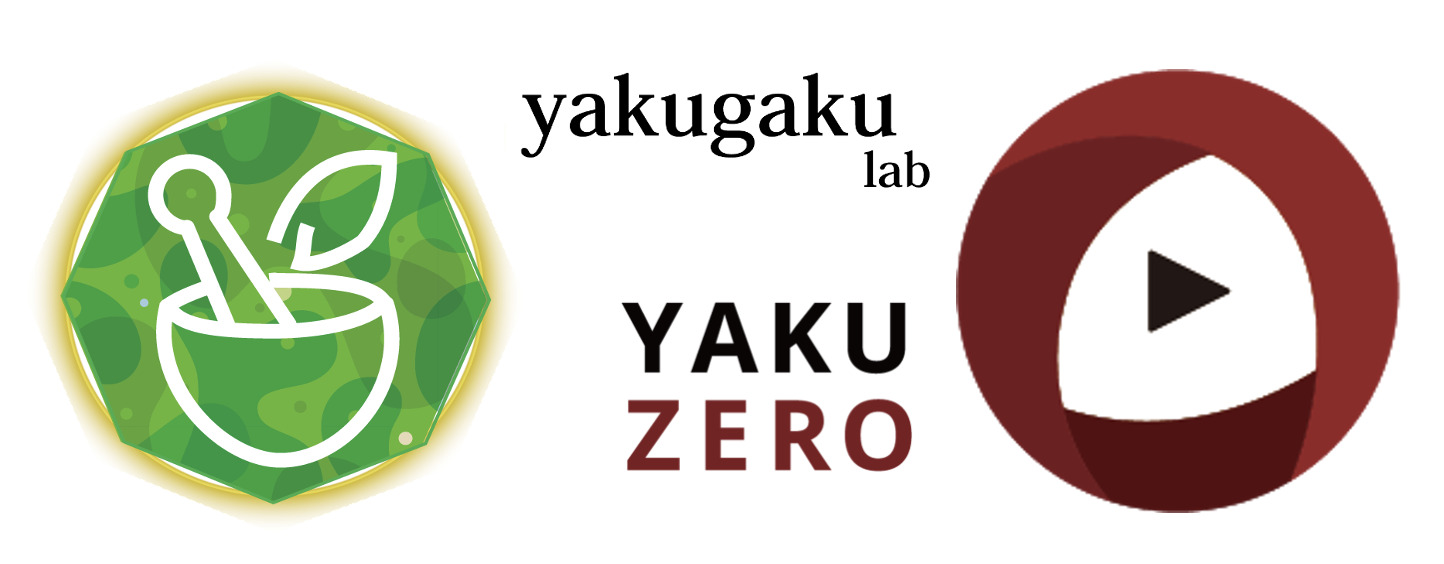

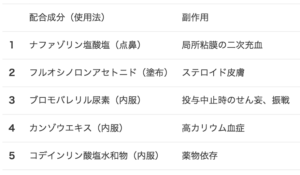
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 第97回 問228〜229 […]