学校薬剤師が授業中の教室の環境に係る検査を実施するため、中学校を訪れた。この学校には冷暖房設備と機械換気設備が設置されている。学校薬剤師は、検知管を接続した測定機器を用いて、2限目の授業が終了する直前に養護教諭立会いのもと、教室内で二酸化炭素濃度を測定した。
(測定結果)
二酸化炭素濃度:1,600ppm
学校環境衛生基準:二酸化炭素濃度は1,500ppm以下であることが望ましい。
問196(実務)
定結果をもとに学校薬剤師が行うこととして、適切なのはどれか。2つ選べ。
- 測定結果が1,500ppmを超えたので、未使用の検知管を使って測定機器の気密性点検を実施する。
- 教室を30分以上換気し、生徒がいない状態で二酸化炭素濃度を再測定する。
- 換気設備の運転時間の検討や工夫を行った後に、換気能力の確認等機械の点検や整備の実施を助言する。
- 重大な健康被害を生じる可能性が高いことを養護教諭に伝える。
- 測定結果に加え、一酸化炭素などの他の汚染物質濃度の測定結果も合わせて、空気清浄度を総合的に評価する。
問197(物理・化学・生物)
二酸化炭素の検出法とその原理に関連する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 検知管法は、 二酸化炭素が酸性溶液に吸収される性質を利用している。
- 検知管法では、検知管に充てんした検知剤中のpH指示薬の色の変化によって二酸化炭素を検出する。
- 二酸化炭素は、赤外吸収スペクトル測定法でも検出できる。
- 二酸化炭素が対称伸縮振動をする場合、 双極子モーメントは変化する。
- 二酸化炭素は、 水素炎イオン化検出器を用いたガスクロマトグラフィーでも検出できる。
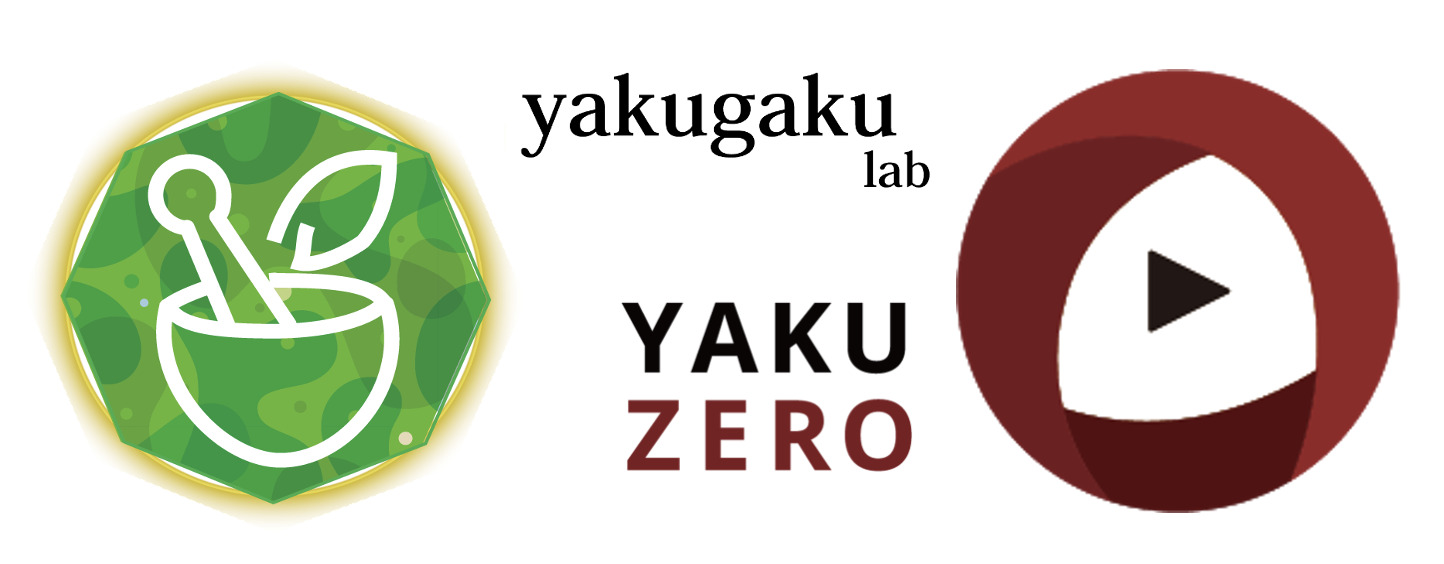


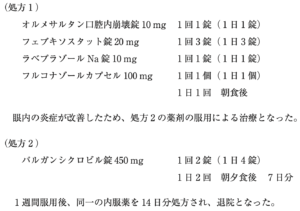


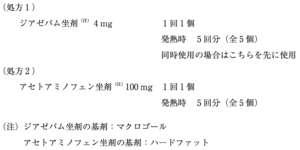

コメント