薬物のみかけの分布容積とその変動に関与する血漿タンパク結合に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- みかけの分布容積は、体内薬物量と血漿中薬物濃度の平衡定数として定義される。
- 特定の臓器や細胞内小器官(核やリソソーム、ミトコンドリアなど)に分布する薬物は、体重1kgあたりの分布容積が10Lを越えることがある。
- 脂溶性の高い薬物の分布容積は加齢に伴って減少する。
- 血漿タンパク結合率が高い薬物のみかけの分布容積は体内水分量とほぼ等しい。
- タンパク非結合型薬物の濃度は、定常状態において血漿中と組織間隙液中との間でほぼ等しい。
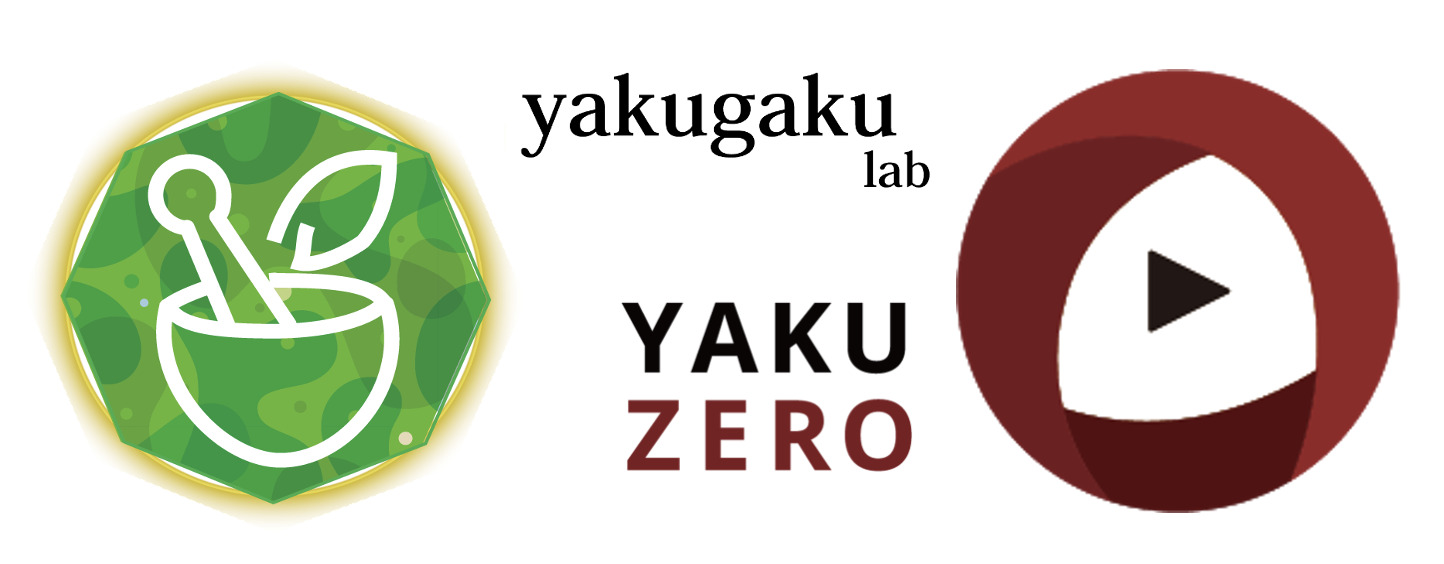


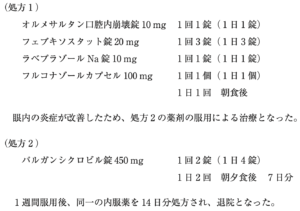


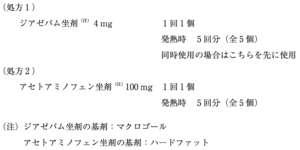

コメント