一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における大気汚染物質の測定法 に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
- 一酸化炭素は、照射した赤外線の吸収量に基づいて測定される。
- 二酸化窒素は、紫外線の照射によって励起した二酸化窒素分子が発する蛍光の強度に基づいて測定される。
- 光化学オキシダントは、ザルツマン試薬との反応により生じる生成物の吸光度に基づいて測定される。
- 二酸化硫黄は、エチレンとの反応により生じる近紫外線領域の発光の強度に基づいて測定される。
- 浮遊粒子状物質は、ろ紙上に粒子を捕集して、β線を照射し、その透過量に基づいて測定される。
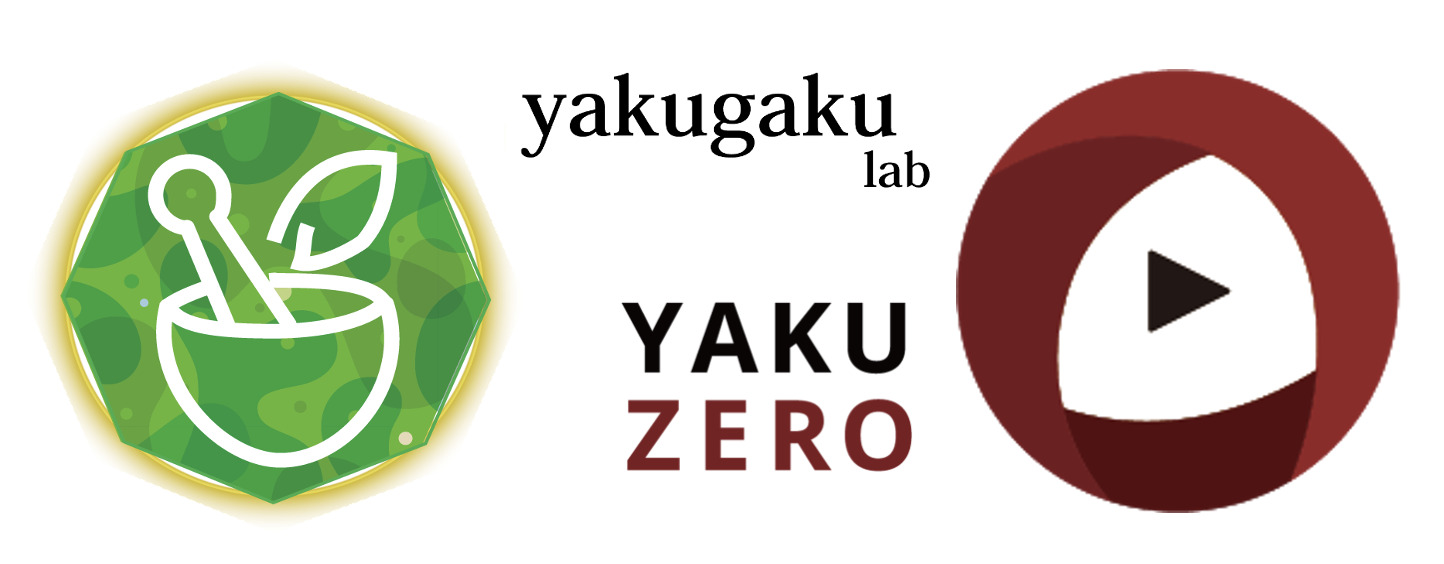


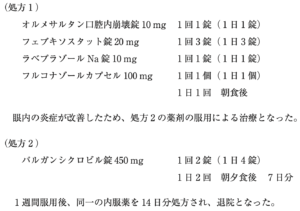


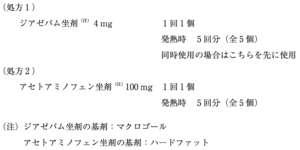

コメント